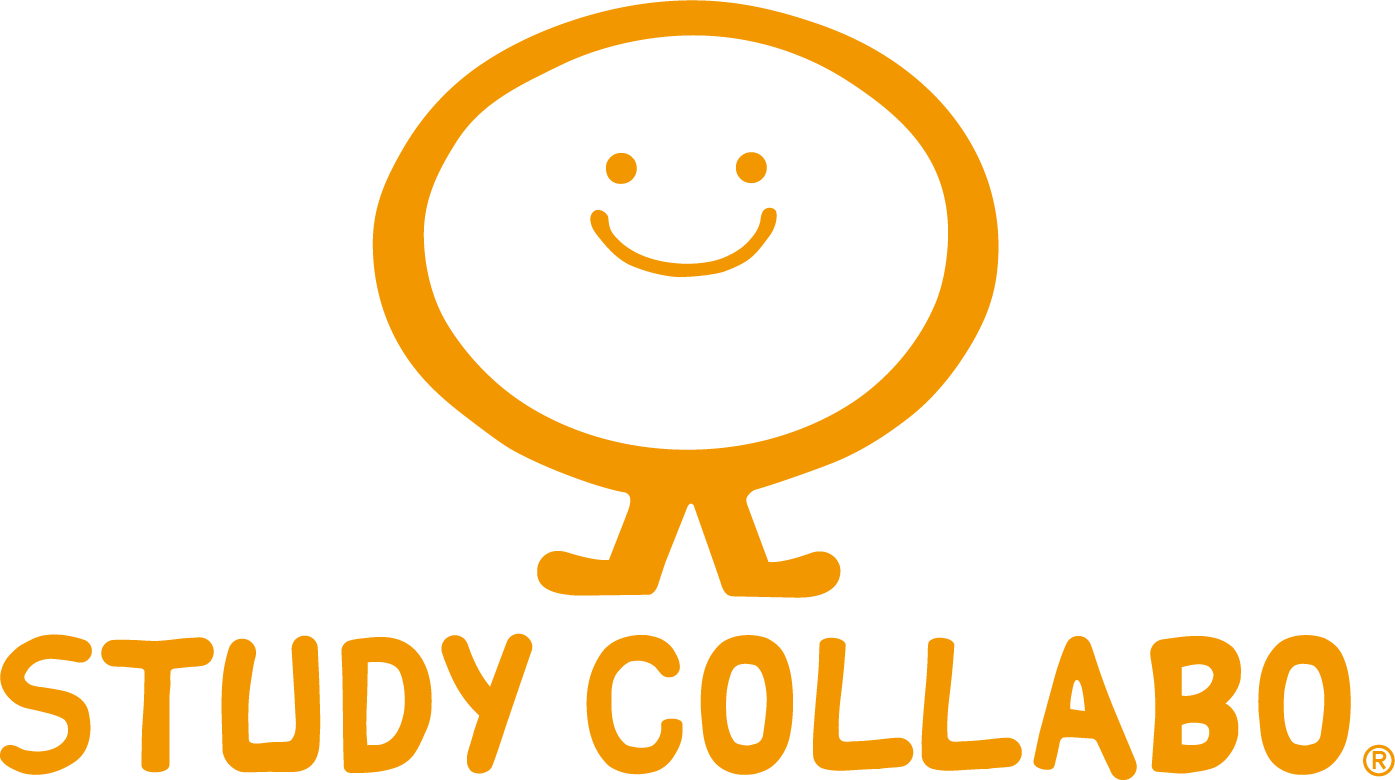[甲陽学院(甲陽)中学の攻略]中1の定期試験対策と勉強法

◆中1生のための甲陽学院中学の英語◆
1学期期末試験の分析
| 1学期中間考査 | コラボ在籍甲陽生平均 | 学校平均 |
| 英語R | 68.5 | 65 |
※英語Wは実施なし
出題範囲は以下です。
| ① Progress in English book1 Lesson4-3~8-3 本文・Look英作文 ② pixis3人称単数・命令文・疑問詞 ③ 基礎英語6月号 |
事前に予告されていた通りのテストでしたが、単語の数が多く苦労した生徒も多い事かと思います。プログレスの進出単語は200個あり、加えて期末テストよりシステム英単語という単語帳がプラスされてありましたので、230個が範囲でした。中間が150個程度でしたので大増加していることになります。定期テストの点数を上げるためには試験範囲の網羅と徹底反復が必要です。甲陽準拠クラスでは準備講座開始の2月より4月、そして中間テストを経て期末テストで高得点を取る為に「単語を書く練習」と「文章を書く練習」を徹底してきました。昨今は書かない生徒も多くその経験値が高平均を支える材料になったと考えています。65点学校平均は10点も下落し、中間のほぼ倍の人数が受講してくれていましたが、平均をクリアーすることができました。
夏休み~2学期中間試験の対策
2学期中間試験に向けては更なる難易度強化+単語追加が見込まれます。教科書範囲はLesson9-1~今のペースでいけばLesson12に突入し、複雑な文法が入り乱れることが予想されます。平均点は60点を切るかもしれません。単語の数は1学期とは比較にならない個数でプログレスだけでも300個は超えてくるでしょう。システム英単語に関しても毎授業ごとにキーセンテンスの空所補充小テストを行っていますが、こちらも継続されていくはずです。次の中間範囲にも必ず入ります。予想単元は「現在進行形」「過去形」「be動詞の過去形」などが範囲になりそうです。もちろん、定期テストなので暗記していると大変有利ではありますが、変化し続ける後の受験対策を考えて、英語学習において最重要なのは暗記ではありません。暗記は「前提」であり、点数を支える土台のようなものです。それがあるのは当然で、生徒達はその上を目指して走っています。学校テストで上位に位置するのは当たり前で、子供たちはさらなる高みを目指し演習をつんでいます。
生徒達は本気の教材だと反応が違います。宿題や小テストの勉強をおろそかにする機会もぐっと減ります。その教材を使い子供たちに常に頭を使わせる授業を行います。授業中に生徒を当て、答えを言わせますので緊張感も段違いです。映像やオンラインの授業と異なるのはここです。生徒が前向きな緊張感の中で頭を使うこと、これが最も肝要です。
「今週はここまでを終わらせよう」「この英作文はこの週に行うからね」「文法の対策はこのプリントを使って今週の土曜日に提出ね」生徒たちにとって必要なのは「上手な解説の先生」でもあり、「次に何をしたらいいか教えてくれるペースメーカー」でもあります。スタディ・コラボの準拠クラスは子供たちが「勉強の仕方」を学び自立できるお手伝いをしています。毎回「今回は何をしようか」などと生徒と相談する授業ではありません。もちろん学校進度のヒアリングは行いますが、カリキュラムや教材がきちんとあって宿題もマメな小テストもあります。生徒達が今週何をすればいいのか迷う事はありません。思えば小学生の塾はそうでした。積まれたプリントの山を一生懸命こなしたことを思い出します。勉強の仕方を伝えるべく正しい試験対策のアプローチをお届けしています。
コラボでの指導法
スタディ・コラボの甲陽準拠クラスは「学校の平均点に到達したい」という生徒が在籍するクラスなので英検や共通テスト対策などは定期テストが終わった回に少し実施しますが、普段はほぼすべて定期テスト対策に注力しています。50点台前半だった生徒が平均を超えて70点台を取れるようになるイメージを抱いてもらうとわかりやすいかと思います。平均プラス5~10点を取れるようになったら大学受験を目指す総合クラスへの編入を促していくクラスです。範囲がなかなか多いので直前期にはヤマを張る生徒も多いですが、それは本来のまっとうな学習とは呼べません。準拠授業中に教科書英作文に注力し、試験前の対策では問題集から出そうな問題をピックアップして重点的に解説しています。
◆中1生のための甲陽学院中学の数学◆
1学期期末試験の分析
中1甲陽の期末試験は英語のラーソン先生の試験がなくなる代わりに,数学三の試験が追加で実施されました。
数学一(数学K:栗本先生)の試験は「方程式,連立方程式」が試験範囲であり,中間試験と同様,「数学の泉」から数学史に関する問題や数学用語を問う問題されました。残りは方程式・連立方程式の計算問題と文章問題がバランスよく出題されており,ほとんどが1度は見たことがある典型問題です。難解な計算や文章問題がなかったため,平均点が82点と,例年の定期試験と比べると非常に易しい試験だったと言えます。今回の試験で点数を落とす原因として考えられるのは,
①分数や小数を含む方程式で計算ミスをする
②数学の泉の暗記内容を覚えていない
③文章問題で方程式を立てられない の3点です。
数学二(数学R:田所先生)の試験は「空間図形の表面積・体積,三角形の合同,二等辺三角形,直角三角形,平行四辺形,比例と反比例」が出題範囲と,非常に広い範囲からの出題となりました。数学二は例年幾何範囲からの出題ですが,代数の進度が遅いためか,代数範囲の「比例・反比例」が数学二の出題範囲に含まれていました。試験問題自体は基本的な問題からの出題が多く,範囲が広い割には平均点が81点と,こちらも易しい試験問題だったと言えます。
数学三は栗本先生範囲50点分+田所先生範囲50点分で合計100点という試験でした。数学三の試験範囲は数学一と二の試験範囲に比べるとかなり限定的でしたが,文字を用いた説明や等式の変形,正誤問題など,やや難易度の高い問題が出題されたために数学一や二ほど平均点が高くはありませんでした。
2学期中間試験に向けた対策
数学K(代数)は「不等式」と「1次関数の前半」が試験範囲だと予想されます。「不等式」の計算問題および文章問題は「方程式」の計算と似ており,1学期期末試験で得点できなかった生徒は早急に復習をしておく必要があります。さらに不等式特有の典型問題もありますので,日々の課題は完璧に仕上げておきましょう。中間試験1週間前にはすべて課題,小テストの解き直しをしてください。学校採用問題集『実力練成 中高一貫体系数学』は解答を配布されていないので,演習が足りない生徒は市販の問題集で演習量を確保しましょう。また,2学期あたりから数学を“本当に理解しているか”で差が開いてきます。今後は計算方法を覚えて手を動かすだけでは対応できなくなります。理解しているかどうかは解いた跡を見れば一目瞭然です。今までのように答えを出すだけではなく,その答えに至る過程を必ず書くようにしてください。これができるかどうかで今後の成績が大きく変わります。
数学R(幾何)は「平行線と面積,相似な図形,線分比」からの出題が予想されます。証明問題は今後も出題が続きます。できたと思っていても,説明が抜けているために減点されることも少なくありません。何をどのように書けば良いのか分からないという生徒は,とにかく模範解答の真似をすることを意識してください。同じような感じで書いているから正解だろうという感覚は注意が必要です。以下の手順で証明の書き方を身に付けてください。
1. 学校・塾の授業で典型問題の証明の書き方を習う。
2. 何も見ずに1.の証明を自分で書いてみる。
3. 2.の答案で抜けている箇所をチェックする。
4. 練習問題(課題)の証明を自分で何も見ずに書く。
5. 4.の答案のチェックをする。先生に添削してもらうことが理想。
証明の答案は添削してもらわないと書けているかが分かりません。学校の小テストでは添削されたものが返却されるので,それをよく見直して,何が足りていないのかを把握しておきましょう。
コラボでの指導法
中1甲陽コンプリート数学のクラスでは、完全に学校に準拠した内容で授業を進めています。基本的には学校の学習内容を少し先取りし,試験前に試験範囲を復習する形です。そうすることにより,コラボで初めての学習⇒学校で2度目の学習⇒コラボの試験前対策による復習と,同じ単元を3度学習することができます。また,普段の授業では宿題範囲からの小テストを毎回実施しています。代数分野でも,今後は記述式試験に変わっていきます。答えが合っているかだけではなく,過程を正しく書けているかも添削によって指導しています。
また,コラボの授業内容以外でも個々に質問対応を行います。授業の前後の時間で質問をする時間がない場合は,web上で質問が可能です。学校の宿題に対するヒントを出したり,アドバイス,証明問題の添削などもここで行っています。
定期試験後の復習も重要です。全生徒に定期試験の点数を報告してもらい,答案を提出してもらいます。間違いが単なる計算ミスなのか,根本的にやり方を間違っていたのか,それらの原因を分析し,指導に生かしています。