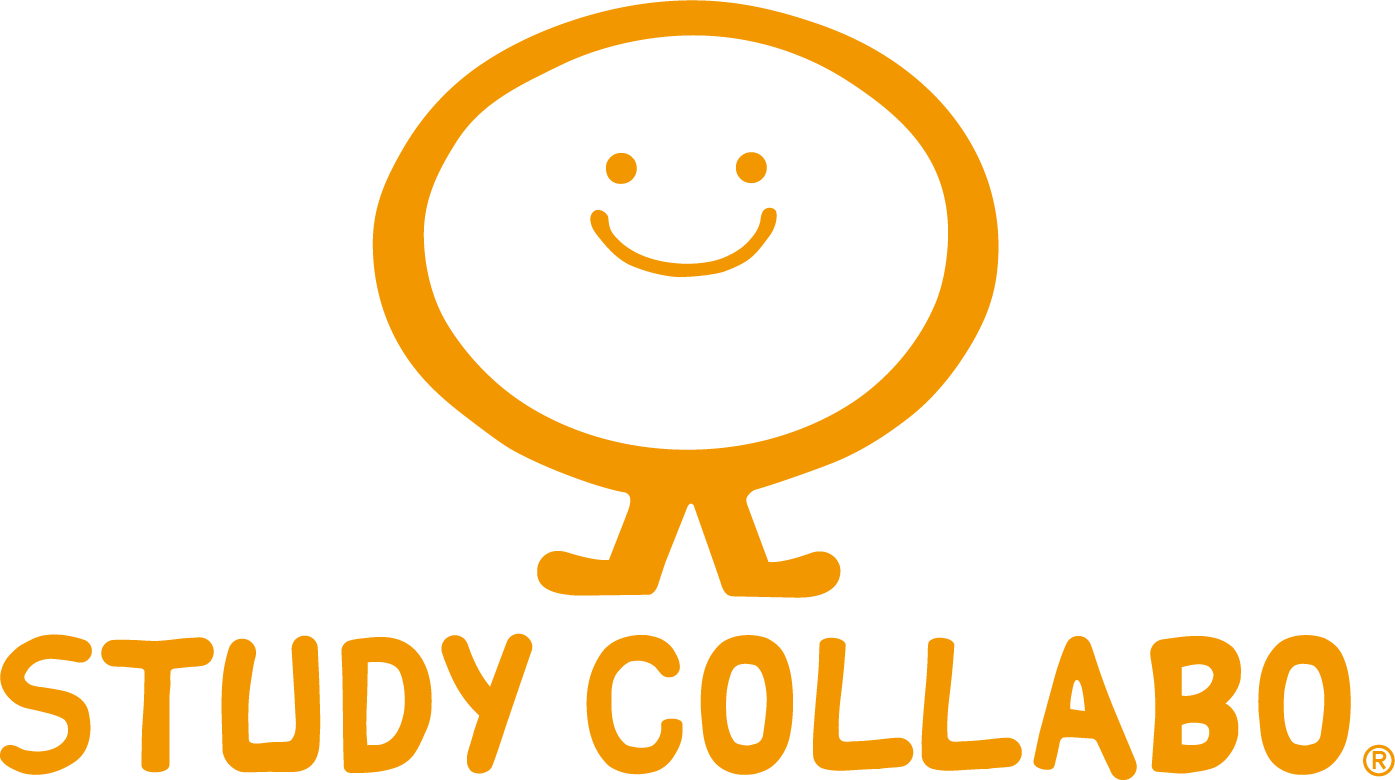[六甲学院中学の攻略]中1の定期試験対策と勉強法

◆中1生のための六甲学院中学の英語◆
1学期期末定期考査について
| 英語1 | 英語2 | 英語LC | |
| 学校平均 ※各クラスにより変動 | 65~68点 | 80点 | 未発表 |
| コラボ平均 | 73点 | 85点 | 27点 |
| コラボ在籍者の最高点 ※2023年7月14日現在 | 82点 | 95点 | 29点 |
英語Ⅰ※S先生
英語1は大問数が6問でした。中間考査ではリスニングは出題されませんでしたが、今回は35点分が出題されました。前回は大問数5問のうち、大問3つは客観式問題であったものの、およそ55点分が記述式だったためスペルミス無く時間内に終えられる構成であったことから、中間考査の平均が80点台だったのは例年通りだったと言えますが、今回の期末では素直な出題であった整序問題で20点分、そして同じ整序問題の部類に入るものの、不足している1語を書かせる問題が10点、知識としてしっかりと勉強してなければ決して点数に結びつかない空所補充に15点、そしていかにも六甲らしい英作文(和文英訳)で20点分という具合に聴き取りと記述の増加により1学期期末考査の平均点が65~68点、即ちおよそ15点平均点が下がってしまったことで一筋縄では解けない構成になったと言えます。
英語Ⅱ※A先生
英語2も大問数が6問でした。特に大問1のリスニングは中間時は20点の配点のリスニングだったのが30点の配点となったため、ここで点数を稼ぎながら大問2や3の知識問題(語彙)で35点、そして大問4の長文(READ文)で30点、大問5では配点は低い設問(各1点×5)であるものの、整序問題の形式において4番目にくる語句を答えさせるものや同じ配点であった大問6の正誤問題の出来不出来が平均点をきちんと超えたかどうか、且つ90点以上の得点ができたかどうかの分かれ目だったと言えます。英語1よりも平均点が高い理由は語彙問題(日⇒英[25点]、英⇒日[10点])でしっかりと稼ぐ生徒が多かったことが主な理由として挙げられます。
問題形式は例年同様に差異なく大きく分類すると以下のように分類できます。
①リスニング問題
会話文の空所20か所を埋める問題
ここでしっかりと得点してほしいことから、3回各英文が読まれました
②語彙問題
Ex) 解答欄に英単語のスペルを書きなさい。※一部抜粋
(1) 日曜日 (2) 土曜日
(3) 8月 (4) 3月
(5) 水曜日 (6) 1月
③和文英訳
Ex) 次の各文を英語になおしなさい。
(1) 私の母は時々、夕食に中華料理を作ります。
(2) あなたは何時に就寝しますか。たいてい9時に寝ます。
(3) このウサギは長い耳を持っていますが、あのネコの耳は短いです。
(4) トムはサンドイッチをいくつほしがっていますか。8つほしがっています。
(5) あちらの背の高い男性達はあなたの兄達ですか。いいえ、ちがいます。
New Treasure Stage1の今後の学習単元
| ※参考(例年の学校進度) 2学期中間テスト → さまざまな疑問詞・所有代名詞・命令文・Can・進行形 |
夏期明け課題・中間考査の対策
問題に使用される文のほとんどは今後トレジャーのKey Pointsと本文で使用されている文になります。つまり、中学のうちはKey Pointsと教科書本文が書ければある程度の点数(平均点)が見込めます。特に中1のうちは徹底して教科書をマスターすることに全力を注がなければなりません。なぜならこの時期はテストでプラスαの知識はほとんど求められず、授業内容に即した出題となっているからです。そのためスタディ・コラボではKey Pointsの解説・演習に多くの時間をかけています。
また文法問題集の存在も決して軽視できません。現時点で教科書や単語帳に時間をかけた分だけ点数に直結していたのが、文法問題集が疎かだと期末以降は平均点を下回る可能性がありますので上記3点は今後欠かさないように努めて下さい。
以下にもありますように、スタディ・コラボの指導法に基づき定期試験応援イベントなどを積極的に活用していただきたいです。
コラボでの指導法
定期試験応援イベントにて学校で学習している文法単元をいち早くマスターしましょう。夏期明け課題考査はbe動詞・一般動詞・疑問詞・副詞がメインとなります。これを混同してしまうケースが多発しますが、「静的」なbe動詞、「動的」な一般動詞という具合に一網打尽できるように指導していきます。また「頻度を表す副詞」を英文のどこに置けば良いかが分からないという声を聞きますが、頻度を表す副詞の位置≒notの位置という具合に決して普段の授業では気付くことのないポイントを教えています。
さらにスタディ・コラボでは定期試験応援イベントにて、学校の試験形式に即した問題演習をはじめ、試験前振替の授業においても同様の問題を解くことに加え過去問情報によりほぼ例年通りに文法単元を変わりなく出題する六甲の対策に最適です。
◆中1生のための六甲学院中学の数学◆
1学期期末試験の分析
<数1>
| 試験範囲 | 少 多 ★☆☆☆☆ |
| 難易度 | 低 高 ★★★★☆ |
| 分量 | 少 多 ★☆☆☆☆ |
試験範囲は学校閉鎖の関係もあってか「文字式」のみとなりました。しかし、平均点が50点を切り、かつてないほどになりました。問題数自体は非常に少なく、ほとんどの問題が計算問題でしたが、その計算問題の大半がとても複雑計算を強いられるものでした。
<数2>
| 試験範囲 | 少 多 ★★☆☆☆ |
| 難易度 | 低 高 ★★☆☆☆ |
| 分量 | 少 多 ★★☆☆☆ |
試験範囲は例年通り、「平面図形」の残りから「空間図形」の途中までとなりました。図形の計量や空間図形など、小学校時代でも経験したことのあるような問題も多く、数1よりは解きやすかったのではないでしょうか。平均点も80点近く出ています。
※コラボ数学授業生の平均点と学校平均点との比較
| コラボ生平均点 | 学校平均点 | 差 | |
| 数1 | 71 | 48 | +23 |
| 数2 | 85 | 78 | +7 |
2学期中間試験に向けた対策
<数1>
次回の試験範囲は「方程式」全般になるものと予想されます。今回の試験を見ても分かるように、計算力が問われる試験になると思われます。したがって、複雑な計算問題を数多く練習しておくことが対策となり、勝敗の分かれ目にもなります。
<数2>
次回の試験範囲は「空間図形」の残りと「角」の計算問題、および「合同と証明」の一部になるものと予想されます。特に証明問題で点差が開きます。証明に関しては自己採点が困難ですので添削指導を受けることが望まれます。
コラボでの指導法
数学においては、上辺だけの理解では到底問題が解けるようになりません。コラボでは双方向型の授業を行い、少人数制を生かして、一人ひとり「わかるまで」、「できるまで」指導を行います。また、定期試験前にはどなたでも受講可能な応援イベント(日曜日に実施)に加えて、総合クラス受講生に関しては試験前対策授業を無料で実施することで、定期試験に向けてもきめ細やかなフォロー体制を整えております。