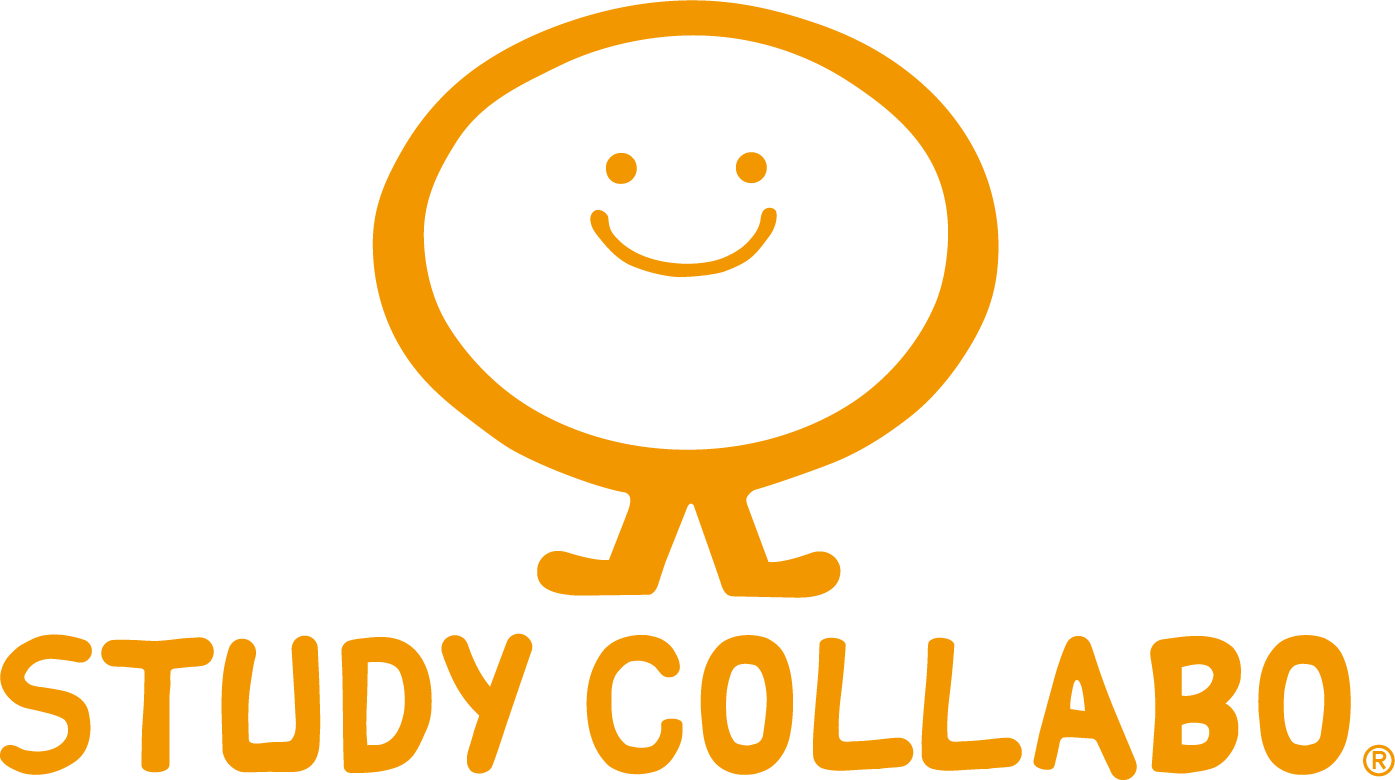[神戸女学院中学の攻略]中1の定期試験対策と勉強法

◆中1生のための神戸女学院中学の英語◆
1学期中間試験の分析
100点満点のテストで、今回の学校平均は90.8点でした。発音記号からアルファベット、ローマ字の書き取り、同じ発音群をグループ分けする問題、授業使用プリントで学習したイラストと英単語の書き取り、単数や複数をしっかりと区別できているかを採点の主眼に置きながら、be動詞を主軸にした肯定文や疑問文、そしてwhat疑問文の書き取りが出題されました。リスニングは32点分が出題され、アルファベットの聞き取りから、位置関係をイラストにして表す問題でした。以下はコラボ在籍者の最高点となります。
| 学校平均 | コラボ在籍者平均 |
| 90.8点/100点満点 | 95.5点(+4.7点) |
例年通り、1学期中間考査の平均点は90点台となるため、かなりの僅差でコラボ生全員が大いに健闘してくれました。一方で、これまで英語学習を重ねており英検取得者でもあった方でも平均を下回った方もいたと思います。それは以下にも記載している通り、教科書を使用しない女学院特有の授業の進め方、ならびに扱われる単語も独特であるためです。しかし心配は不要です。スタディ・コラボでは定期試験講習会にて、学校の試験範囲の問題演習を行います。最後の仕上げとして、試験前日に実施する直前対策で予想問題を解くことに加え、過去問情報によりほぼ例年通りに文法単元を変わりなく出題する女学院対策に最適だからです。
試験範囲と出題内容
1.アルファベットとローマ字の書き取り
2.発音記号に基づくグループ分け
3.イラストと英単語の書き取り
4.単数・複数の区別
5.be動詞を主軸にした肯定文・疑問文、what疑問文の書き取り
6.リスニング(32点):アルファベットの聞き取り、位置関係をイラストに表す問題
使用教材と授業スタイルについて
神戸女学院中の英語の授業は、他校と比べて異彩を放っています。女学院中では「英語を英語で学ぶ」ことが徹底されており、教材はほぼ全て英語で書かれたオリジナルプリント、授業の進行・生徒に与えられる指示も原則として英語です。また「英語を実用に即して学ぶ」ことにも主眼が置かれています。最初は学習した文法事項をドリル形式で演習しますが、すぐに「絵を見て状況を描写しなさい」「以下の質問に対する答えを書きなさい」など、会話・英作文を中心にした活動が主になります。とはいえ、最初の進度はそれほど速くありませんでした。1年生の1学期のうちは、正しいつづり方・発音を身に付けることに主眼が置かれており、発音記号と正しい発音、単語のスペルを徹底して叩き込まれたはずです。「絵を見て単語を答える」「発音記号を見て単語を答える」といった活動が続くので、英検取得者にとっては単調かつ退屈だったかもしれませんが、次回の1学期期末考査の勉強からそう言っていられないのではないでしょうか。定期試験のリスニングでは、聴き取った英文を英語で表記する“Dictation”が求められることがさらに増えてきますので、1学期中間に行なった発音練習を疎かにしてはいけません。1学期中間で音とつづり、英作文の基本ルールをマスターして来たる2学期開始時より本格的に英文法の学習が始まります。文法項目の分類・序列は、日本で発刊されているテキストのそれとは異なる部分が多いのですが、これも女学院の伝統と割り切って受け入れることが必要です。
参考として、以下に中1女学院の年間の授業進度の例を示しています。特に今後の単元をチェックしてみましょう。
| 英語 | |
| ~1学期中間 | ・アルファベット・英作文のルール・発音記号 ・単語の学習・be動詞の文 (this / that is ~) |
| 1学期中間 ~1学期期末 | ・be動詞の文(these / those are~) ・前置詞・疑問詞 (where, what) ・形容詞・助動詞 (can)・命令文 |
| ~2学期中間 | ・疑問詞 (what time~)・一般動詞 ・比較・未来の文 |
| 2学期中間 ~2学期期末 | ・接続詞・助動詞 (may, should) ・be動詞・一般動詞の過去形 |
| 3学期末まで | ・形容詞(+比較の復習)・感嘆文 ・不定詞(名詞的用法のみ)・読解問題 |
1学期期末試験にむけて
①やはり単語力がモノを言う:
定期試験までに授業で教わる単語は、基本的に発音記号・つづり・日本語の意味、全てを覚えるよう努力しましょう。特に1年生の間は、定期試験の中で単語が占める割合が非常に多いです。結果、初期(1学期~2学期)の定期試験ではスペルミスが点数の良し悪しを分けました。この時期は、単語を正しく綴ることが最重要課題です。オリジナル教材に登場した単語はもちろん、先生が授業内で言及された単語までもすべて覚えるつもりで授業に臨んでください。さらに、発音記号の問題も毎年出題されています。単語を調べる時は意味や綴り字だけでなく、発音記号とアクセントも確認してください。それには「英和辞典」が必要です。辞書を引く習慣があるかないかが、将来的に英語が得意になるか否かの分かれ道です。
② 日々の授業を大切にすることが、高得点の第一歩:
1学期の中間試験ではbe動詞(現在形)の肯定文/否定文/疑問文(および、その応答文)が主な試験範囲となりました。主語の人称によるbe動詞の活用(am/are/is)を確認することはもちろん、不定冠詞の使い分け(a/an)、名詞の単数・複数に注意できているか今一度気を配りましょう。
期末試験では、疑問詞/命令文/現在進行形/助動詞(can)あたりまで出題されました。いずれも単独項目だけでなく、複合的・有機的な形式が多く見られます。例えば、疑問詞と現在進行形が融合したWhat are you doing now?等です。現在進行形では「(be動詞)+(現在分詞)」の形を取るので、主語の人称、単・複によりbe動詞が変化します。つまり、be動詞の活用が身に付いていて初めて先の英文を書くことができるのであり、それが得点に繋がるわけです。
女学院の授業は同じ文法単元を繰り返して練習しつつ、既存の知識の上に少しずつ新しい事項を塗り重ねていくという形を取っています。従って、試験前に一人で勉強しようとしても大変効率が悪く、ヌケモレが多々出てしまいます。定期試験で高得点を取るには、日々の授業は完全に理解した状態でいなければなりません。特に授業は指示も説明も全て英語ですから、「一体この授業では何をやっているの?」という状態に陥らないよう、不明な点はその都度解決して、試験まで持ち越さないようにしたいものです。
③リスニング対策を後手に回さない:
女学院の試験では必ずリスニングが課されます。1年生1学期の聞き取りテストは、それほど難しいものではなかったと思います。とはいえ、聴き取りができても、正しく設問に答えられなければ得点にはなりません。聞き取れはしたけど綴りが違った、答えを勘違いした、肝心なところが聞けたか自信がない…という状態では、学年が上がるとすぐにリスニングが苦手になってしまいます。外国語は全身を使って習得するものです。今のうちから「英語は目で見る・耳で聞く・手で書く・声に出す(音読)」といった習慣をいち早く身につけましょう。自分で行なう学習のうちにこの習慣が組み込まれた生徒は、リスニングはもちろん、会話も比較的スムーズにできるようになるでしょう。
④スタディコラボの応援イベント教材等を完璧にする:
限られた時間内で単語や英文を正確に書くには、日頃から自分が間違えやすいポイントを知ることが必要です。これまでの試験は出題範囲が狭いため、点を取りこぼす原因はケアレスミスだと言っても過言ではありませんでした。ふだんから、答え合せをする前に見直す癖をつけ、「わかっていたのに間違えた」箇所をなくす注意力を高めましょう。結局のところ、英語の点差は「注意力の差」なのです。「今回はたまたま間違っただけ」、「本番では大丈夫」、そんな言い訳をよく耳にしますが、そういう生徒は必ずと言っていいほど、本番でもミスを犯すのです。自分のミスを謙虚に受け止め、その傾向を把握し、たゆまぬ努力を続ける。これこそが語学の王道です。
コラボでの指導法
総合クラスの授業時間は100分です。使用テキストは主に「実力錬成テキスト」を用いて文法単元の先取りを学習していきます。また語彙の勉強も欠かすことはできませんので、こちらはValue1000(数研出版株式会社)にていち早くおおよそ英検3級レベルまでの語彙を付属のCDを用いて勉強してもらいます。もちろん知識の確認を行うため毎回15分の小テストは欠かせませんし得点率が7割を下回れば再テストも実施します。コラボの授業は女学院とは異なり日本語で英語の授業を行います。先取り学習をすることで学校の進度よりも先を学習すれば英語で触れる学校の授業でも迷うことはありませんし、気持ちの余裕が生まれます。定期考査直前は応援イベントや試験前対策講座にて数回本番の試験内容に即した問題演習を通して、知識の定着をはかります。分からない問題は講師に積極的に聞いて下さい。
◆中1生のための 神戸女学院の数学◆
1学期中間試験の分析
・代数
代数の試験範囲は正負の数のみでした。女学院の1学期中間試験としては例年と同一の範囲です。
試験範囲が狭い分、正負の数の理解について様々な観点から幅広く問う問題が多く出題されています。未知数の符号判定など高度な思考力を求められる問題も含まれており、単純に正負の数の計算ができるだけでは良い得点が得られない試験となっていました。その中でも平均点は78点と、初回の試験から点差が大きく開く結果となっているようです。
特に出来が分かれたと思われる問題が、大問7です。これについては問題文で与えられた情報を1つ1つ丁寧に吟味し、複数の情報を組み合わせて正答を導き出す必要があり、女学院らしいレベルの高い問題と言えます。条件を満たす数を「全て」答えさせる問題も多く、漏れなく解答できたか否かがポイントでした。
・幾何
幾何の試験範囲は、平面図形でした。代数同様、試験範囲としては狭い部類に入ります。全体的な難易度は高くなく、平均点は90点と非常に高く出ています。しかし、作図に関しては、抽象的な問いから具体的にどのような作図をすべきかを判断する必要性がある問題となっていたためここで差が出たのではないかと予想します。
1学期期末試験の対策
代数分野については、今後文字式・方程式を扱っていくことになります。文字式を用いた表記のルールや、係数・次数・項といった数学用語の意味を理解し、いち早く文字式の扱いに習熟することが中間考査後最初の課題となります。その後は様々な量を文字式で表現する問題を扱います。小学校で学習した割合が絡んできますので、苦手な方は復習が必要です。方程式については例年高度な文章題を解くレベルまでの習熟が求められていますので、学校教材よりもワンランク上の問題集で演習を積んでいくのが理想的です。
一方、幾何については、今後空間図形の内容に入っていきます。平面図形と比べてイメージするのが難しい内容ですが、扱うレベルはやや高度です。特に正多面体の問題や、直線と平面の位置関係の正誤問題は例年出されていますので、徹底した対策が必要です。
コラボでの指導法
現在、神戸女学院は専用の準拠クラスを設置しておりませんので、総合クラス(集団授業)で大学入試を見据えた先取りの学習を進めるパターンか、個別指導で学校に合わせた学習をしていくパターンかに分かれます。いずれの場合も授業においてはコラボ専用テキストを主として使用しており、テキストには学校教材よりも少しレベルの高い問題も収録しています。こうした応用問題で実力を養うことが、学校試験の応用問題で得点することに繋がります。
定期試験前には中1女学院の生徒さま対象に予想問題を用いた演習を行っています。
1学期期末試験に向けての対策講座もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。